高齢の親が運転をやめると、日々の通院・買い物・外出など、生活に大きな影響が出ます。特に地方や坂の多い地域では、車がない生活は困難を極めるケースも少なくありません。一方で、子ども世代が「どうサポートすればよいか分からない」「負担が増えるのでは」と悩むことも…。
本コラムでは、親の免許返納後に直面しがちな「移動手段の問題」や「生活の不安」に対して、具体的な選択肢と支援制度、地域サービスの活用方法をわかりやすく解説します。移動支援・買い物代行・通院サポート・福祉輸送サービスなど、多様な支援を組み合わせることで、親の安心と家族の負担軽減を両立する道を探っていきます。
- 高齢の親が免許返納を検討・決断したご家庭の方
- 地方や車依存の高い地域に住んでいる親を持つ子ども世代
- 「親の生活をどう支えるか」で悩んでいるご家族
- 移動手段や地域支援サービスの情報が知りたい方
- 将来的に親の介護・送迎に備えたいと考えている方
- 免許返納後に直面する現実的な課題と対策がわかる
- 親の移動支援や生活サポートの具体的な選択肢が見えてくる
- 地域で利用できる制度や支援サービスが理解できる
- 家族が無理なく協力できる仕組みの作り方が学べる
- 生活支援つき身元保証など、プロのサポートの活用方法がわかる
【親が車を手放した後の生活設計】
高齢者の“移動手段”をどう確保するか

高齢者が車を手放す大きな理由の一つが、「安全の不安」です。運転ミスによる事故の報道が相次ぐ中、家族や本人が「もう車は危ない」と判断することも少なくありません。しかし、車が生活に欠かせなかった方にとって、それを手放すことは、単なる移動手段の喪失だけでなく、“自立”を一部手放すことでもあります。
そこで重要なのが、「代わりとなる移動手段の確保」です。以下のような選択肢があります。
- 地域のコミュニティバスや乗合タクシー:自治体が運営する移動サービスで、料金も安価。病院・買い物施設を経由する路線が多く、使い勝手もよい。
- 福祉タクシーや介護タクシー:要支援・要介護認定を受けていれば利用可能。車椅子対応車などもあり、安全性が高い。
- 家族の送迎・地域の支え合い:近隣住民やボランティア団体が協力し合って移動支援を行う事例も増えている。
- 電動アシスト自転車や歩行サポート機器の活用:短距離であれば自力で移動できる手段の検討も選択肢になる。
大切なのは、「親が無理なく続けられる方法」を一緒に模索することです。
車のない生活における“日常”の見直し

車を手放すと、「買い物」「通院」「友人との交流」「趣味活動」など、さまざまな日常行動が制限される可能性があります。これを機に、生活圏の再構築を考える必要があります。
たとえば以下のような方法があります:
- 宅配サービス(生協・ネットスーパー)を活用する
- クリニックや薬局の訪問診療・配薬サービスを使う
- デイサービスを活用して、外出や交流の機会を維持する
最近では、「買い物代行」「スマホでの処方箋予約」「オンライン通話での友人との会話」など、デジタル活用による新たな日常スタイルも注目されています。高齢者がこうしたサービスに慣れるにはサポートが必要ですが、日々の生活の選択肢が増えることで、ストレスや不安の軽減にもつながります。
住環境を見直すタイミングにもなる
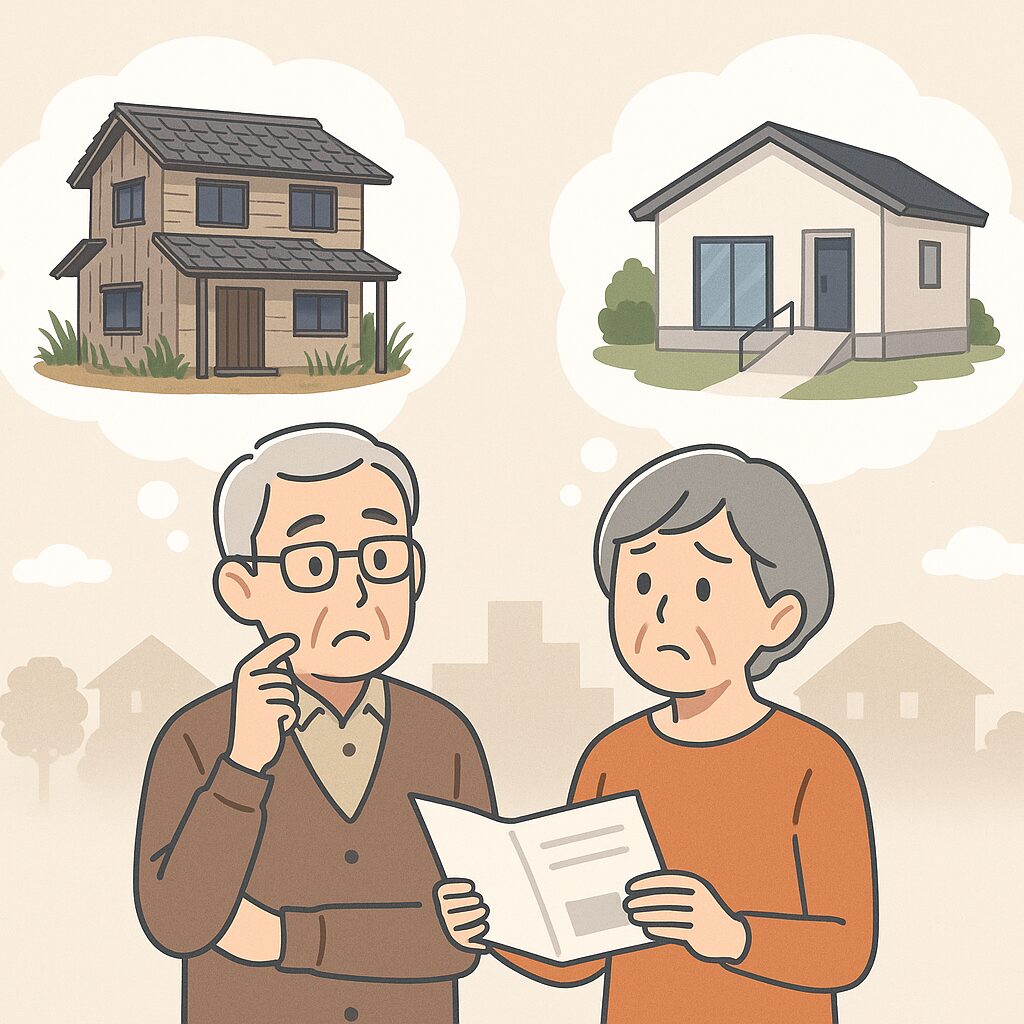
車を手放すことで、「今の家にこのまま住み続けられるか?」という住環境の課題も顕在化します。特に郊外や山間部に住んでいる場合、公共交通が少なく、日常生活のハードルが一気に上がるケースもあります。
こうした状況では、
- 生活圏の中にある高齢者向け住宅や施設への移住
- 駅や商業施設の近くにある“便利な立地”への住み替え
- 自宅をバリアフリー化して、デリバリーや通院支援と組み合わせて暮らし続ける方法
などを家族と共に考える時期になります。
将来の介護や医療のニーズも踏まえ、「数年後を見据えた住まい選び」を始める良い機会になるかもしれません。
精神的・社会的な“つながり”を切らさないために

車は単なる移動手段ではなく、「自由」「交友」「自尊心」の象徴でもあります。これを失うことで、孤立感や無力感を感じる高齢者も少なくありません。
そのため、以下のようなケアも必要です。
- 近所付き合いや地域行事への参加機会を維持する
- 高齢者サロンや体操教室、趣味の教室に通う(送迎サービスつき)
- 地域包括支援センターや生活支援コーディネーターとの連携を強化
これにより、移動の制限を感じにくくなり、社会的な孤立を防ぐことができます。
“生活支援つきの身元保証サービス”という選択肢

親の暮らしを支えるうえで、「誰が支援するか」が将来的な課題になります。そこで注目されているのが、身元保証+生活支援がセットになったサービスです。
たとえば、グループ企業である「微笑堂」が提供する身元保証サービスでは、以下のような支援も行っています。
- 通院・買い物の付き添いなどの日常支援
- 突然の入院・施設入居時の緊急対応
- 施設入所後の家の整理や処分、売却サポート
こうしたサービスを活用することで、「いざという時、誰に頼ればいいか分からない」という不安を解消しやすくなります。家族の負担を減らしながら、親自身の安心感も高められる実例です。 このように、車を手放すことは“終わり”ではなく、“新しい暮らし方の始まり”です。高齢者本人の希望を大切にしながら、家族が寄り添い、地域資源や専門サービスとつながることで、前向きな生活を築いていけます。
実際の体験談:郊外在住の母が免許返納。家族で支えた“第二の暮らし方”

東京都町田市に住む佐藤さん(仮名)のご家庭では、70代後半のお母様が運転免許を返納する決断をしました。山あいの住宅地に自宅があり、最寄りのスーパーや病院までは車で10〜15分。長年、自家用車が“足”として生活を支えてきました。
・「ある日、母がガードレールに擦ったのがきっかけでした」
佐藤さんのお母様は、ある日自宅近くの細い道で、対向車を避けようとしてハンドル操作を誤り、ガードレールに車を擦ってしまいました。大きな事故には至らなかったものの、「反射神経が鈍っている」「自信がなくなった」と話し、家族と話し合いの末に免許返納を決意。
・最初は「生活が成り立たない」と混乱
しかし、実際に車がなくなると、買い物・通院・趣味の外出すべてに支障が。バスは1時間に1本、タクシーは捕まりづらいエリアで、当初は「もう外出できない」と落ち込むこともあったそうです。
・家族で“支援体制”を作って乗り越えた
佐藤さんと妹さんは相談し、以下のような対策を講じました。
- 生協の宅配を契約し、週2回の食材・日用品配達をスタート
- 主治医の訪問診療への切り替え
- 母の通院や外出には、隔週で家族が交代で付き添う体制に
- デイサービスを利用し、週1回の外出&交流機会を確保
さらに、地域包括支援センターに相談したところ、町内の福祉送迎ボランティアサービスを紹介され、今では月に2〜3回の利用も定着しました。
・「意外と暮らせるね」と母も前向きに
こうしたサポートの中で、お母様自身も「車がなくても暮らしていける」と実感し、今では近所の友人と一緒にバスで買い物に行くことも増えているそうです。
よくある質問(FAQ)
.jpg)
Q:親が免許返納を渋っていて困っています。どう説得すればいい?
A:まずは感情をぶつけるのではなく、「心配している」という気持ちを丁寧に伝えることが大切です。
高齢ドライバーの多くは「まだ運転できる」と考えています。家族としては、本人を否定するのではなく、「事故に巻き込まれたら悲しいから」「今なら余裕を持って代替手段を考えられるよ」といったポジティブな言葉を使い、時間をかけて話し合う姿勢が効果的です。
Q:運転をやめたら、買い物や通院はどうすればいい?
A:地域には高齢者向けの支援サービスが意外と充実しています。
移動販売・福祉タクシー・訪問診療・宅配サービス・買い物代行など、地域包括支援センターに相談することで、各自治体の支援制度や民間サービスを紹介してもらえます。家族の送迎だけに頼らない仕組みづくりを意識すると安心です。
Q:車を手放した後、売却や処分はどうするの?
A:買い取り業者に査定してもらいましょう。
車の状態によっては、数万円〜数十万円で売却できるケースもあります。高齢者向けに出張買取を行っている業者もあるので、本人の負担を軽くするために活用を検討しましょう。また、任意売却やリサイクルに関する費用・手続きのサポートがある業者を選ぶと安心です。
Q:公共交通が不便な地域ではどうしたら?
A:民間送迎サービスや地域交通支援の導入を確認しましょう。
最近では、NPOや地域住民の協力で運営されている「おでかけ支援サービス」や「シルバーカーシェア」なども登場しています。住んでいる地域の行政窓口や包括支援センターに相談すれば、利用できる制度を教えてくれます。
Q:万一、認知症が進行していたら?
A:免許の自主返納に加えて、法的なサポートも視野に入れましょう。
判断能力の低下が見られる場合は、「任意後見契約」や「成年後見制度」の活用を検討すべきです。また、親の今後の生活設計について早めに家族で話し合い、意思決定支援を行うことが望ましいです。
なお、親御さんの生活支援や施設入居などで不安がある場合は、グループ企業である「微笑堂」の身元保証サービスもご活用いただけます。
微笑堂の身元保証は、入院・施設入居時の保証人代行だけでなく、日常の生活支援(買い物や通院同行など)まで含まれているのが特徴です。
高齢の親が車を手放し、移動手段や生活に不安を感じた際には、こうした包括的な支援サービスを利用することも選択肢のひとつです。
詳しくは、微笑堂の公式サイト(https://www.hohoemido.com/)をご覧ください。
まとめ

高齢の親が車を手放すという決断は、単なる「運転をやめる」という話にとどまらず、その後の生活や移動手段、地域との関わり方、そして家族の在り方にも大きな影響を与えます。
免許返納をきっかけに、家族での話し合いや今後の生活設計を見直すことは非常に大切です。とはいえ、仕事や家庭を持つ子ども世代にとって、親の暮らし全般を支えることは、時間的にも精神的にも大きな負担となることもあるでしょう。
そんなときこそ、専門家のサポートを活用してください。
株式会社昇永のサポート
株式会社昇永(しょうえい)は、シニア世代やそのご家族の「困った!」を丸ごとサポートするワンストップサービスを提供しています。
- 親が車を手放した後の生活設計
- 移動支援や地域サービスの紹介
- 施設入居・住み替え・不動産売却のサポート
- 任意後見契約・遺言書の作成支援
- 介護保険の利用や生活支援サービスの相談
- 遺品整理・生前整理・空き家問題の対処 など
お困りごとがひとつでもある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
グループ企業「微笑堂(ほほえみどう)」の身元保証もおすすめです
生活に不安を感じる高齢者の方や、そのご家族から特に支持をいただいているのが、グループ企業・微笑堂の「身元保証サービス」です。
入院・施設入居時の保証人代行だけでなく、日々の生活支援(買い物同行、役所手続き代行など)も充実しており、孤立しがちな高齢者の「暮らしの安心」を支えています。
詳しくは、微笑堂の公式サイト(https://www.hohoemido.com/)をご覧ください。
お問い合わせ・ご相談はお気軽に
株式会社昇永では、メール・電話・LINEからのご相談を受け付けております。
初回のご相談やお見積もりは無料です。
【昇永へのお問い合わせはこちら】
相談無料のお問い合わせフォーム
LINEからでもお気軽なお問い合わせが可能です
【昇永のサービスで、あなたとご家族に安心を】
お気軽にご連絡ください。あなたの“これから”を、昇永が一緒に考えます。
