高齢者の方が自宅をリフォームする際の資金問題を解決する選択肢に、住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例制度」があります。
この制度は、毎月の返済が利息のみで負担が軽く、申込時の年齢上限もないため、年金収入の方や年齢を理由にローンを諦めていた方でも利用しやすいのが特徴です。
例えば、手すりの設置などのバリアフリー工事や、地震に備える耐震改修工事などを、資金面の不安を軽減しながら実現できます。
本記事では、制度の仕組みやメリット・デメリット、注意点を詳しく解説します。
リフォーム費用の借入にお悩みのご本人やご家族の方は、ぜひ最後までご覧ください。
リフォーム融資「高齢者向け返済特例制度とは」
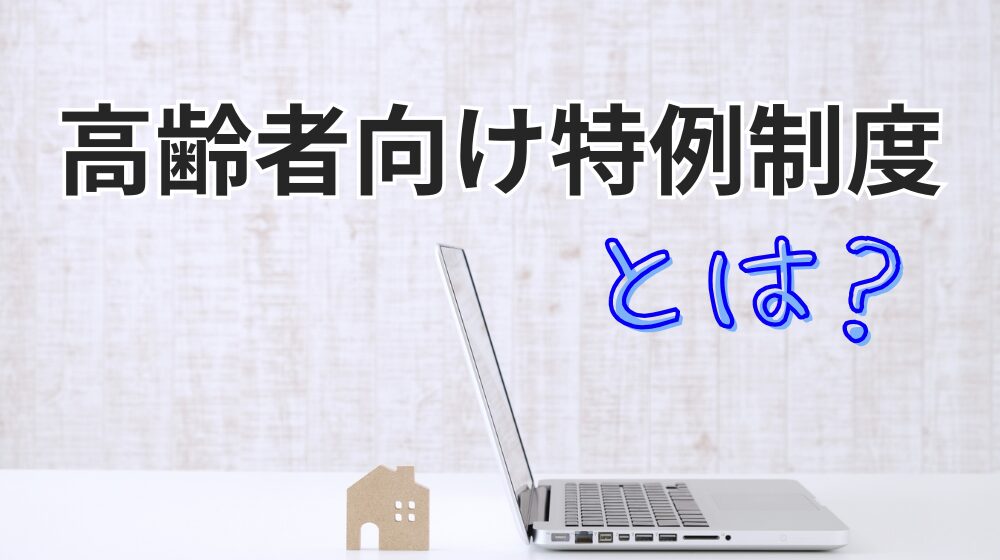
高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の方が自宅のリフォームをおこなう際に利用できる融資制度です。
この制度では、毎月の返済を利息のみに抑え、借入金の元金は申込者全員が亡くなった際に一括返済となります。
【参考】 (一社)日本建材・住宅設備産業協会「公的支援使っていますか?」
この制度は、住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)が提供する公的なもので、一般的なリフォームローンとは異なり、収入が年金のみの方でも利用しやすい特徴があります。
対象となるリフォーム工事は、次のいずれかを含むものです。
- バリアフリー工事
- ヒートショック対策工事
- 耐震改修工事
【参考】住宅リフォーム推進協議会「リフォームのお得な制度」
【参考】リフォーム融資(高齢者向け返済特例)「京すまいの情報ひろば」
これらの工事をおこなうことで、高齢者の方々が安心して暮らせる住環境を整えることが可能です。
高齢者がリフォームローンを借りる際の課題と解決策
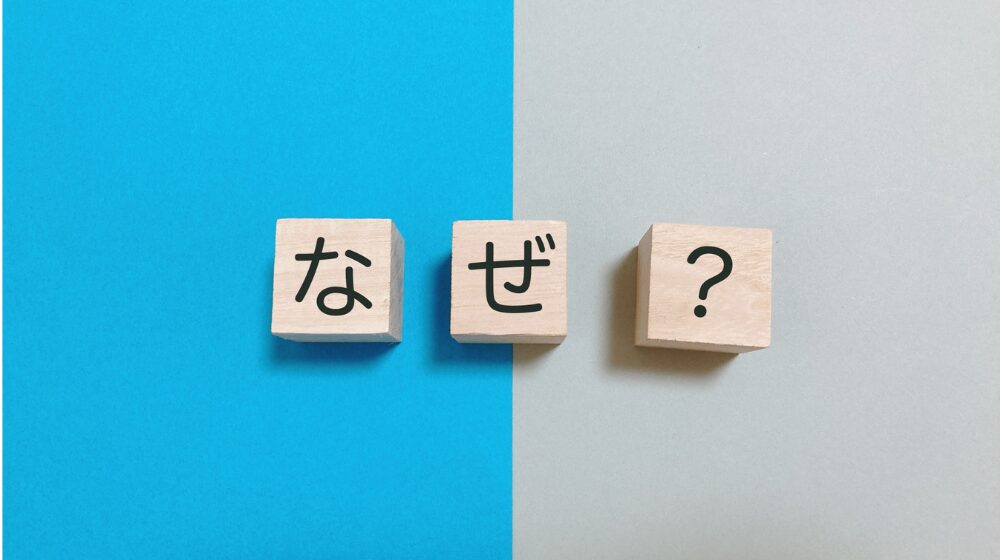
高齢者がリフォームローンを利用しようとする際には、金融機関の審査基準や返済計画、将来的な生活設計など、さまざまな観点から検討が必要となります。
特に、従来型のローン商品では、次のような課題への対応が難しいのが現状です。
【年齢制限で融資を断られる】
多くの金融機関では、融資時や完済時の年齢に制限を設けており、高齢者が新たなローンを組む際の障壁となっています。
【年金収入による返済能力の評価】
年金収入のみの場合、返済能力が低いと判断され、希望する融資額を受けられないことがあります。
【将来の返済に対する不安】
高齢者は将来の収入や健康状態の変化により、長期的な返済に不安を感じ、リフォームを躊躇することがあります。
【子どもへの負担を懸念】
自身の借入が将来的に子どもに負担をかけるのではないかと心配し、ローン利用をためらうケースも見られます。
これらの課題に対する解決策として、「高齢者向け返済特例制度」の活用が挙げられます。
この制度では、毎月の支払いを利息のみに抑え、元金は申込人全員の死亡時に一括返済となるため、月々の負担を軽減できます。
また、住宅金融支援機構が提供する公的制度なため、一定の条件を満たせば利用が可能です。
さらに、リフォーム後の住宅価値向上により、将来的な資産価値の増加も見込めるでしょう。
【参考】住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)「リフォーム融資【高齢者向け返済特例】(部分的バリアフリー工事・ヒートショック対策工事・耐震改修工事)」
このように「高齢者向け返済特例制度」を利用することで、高齢者が抱えるリフォームローンに関する課題を克服し、安心して住環境の改善を図ることが可能です。
高齢者向け返済特例制度とリバースモーゲージの違い

高齢者向け返済特例制度とリバースモーゲージは、いずれも高齢者が自宅を担保に資金を調達する方法ですが、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 高齢者向け返済特例制度 | リバースモーゲージ |
|---|---|---|
| 返済方法 | 毎月利息のみ返済、元金は申込者全員の死亡時に一括返済 | 毎月の返済なし、契約者の死亡時に一括返済 |
| 融資額の決まり方 | 「1,500万円」または「財団が定める保証限度額」のいずれか低い額 | 年齢や物件価値によって決定、年齢が高いほど融資額が大きくなる傾向 |
| 対象となる工事や用途範囲 | バリアフリー工事、耐震改修工事など特定のリフォーム工事 | 生活資金全般に使用可能で、用途の自由度が高い |
| 相続時の影響 | 相続人が一括返済または担保物件を売却、リフォーム後の住宅価値が上がる可能性あり | 相続人が一括返済または担保物件を売却、融資額が増加し続ける場合あり |
リバースモーゲージとは?
※リバースモーゲージとは:高齢者が自宅を担保に金融機関から融資を受け、契約者の死亡時に自宅を売却して借入金を一括返済する仕組みのローンです。これにより、住み慣れた自宅に住み続けながら、老後の生活資金やリフォーム費用などを調達することが可能です。
高齢者向け返済特例制度はリフォーム工事に特化しており、毎月の利息支払いが必要です。
一方、リバースモーゲージは生活資金全般に使用でき、毎月の返済がない点が大きな違いです。
融資額については、高齢者向け返済特例制度では上限が設定されていますが、リバースモーゲージでは年齢が高いほど融資額が大きくなる傾向があります。
また、相続時の影響も異なり、高齢者向け返済特例制度では、リフォーム後の住宅価値が上がる可能性があります。
自分の状況やニーズに合わせて、どちらの制度が適しているかを検討しましょう。
リフォーム目的であれば高齢者向け返済特例制度、より幅広い用途で資金が必要な場合はリバースモーゲージが適している可能性があります。
高齢者向け返済特例制度の4つのメリット
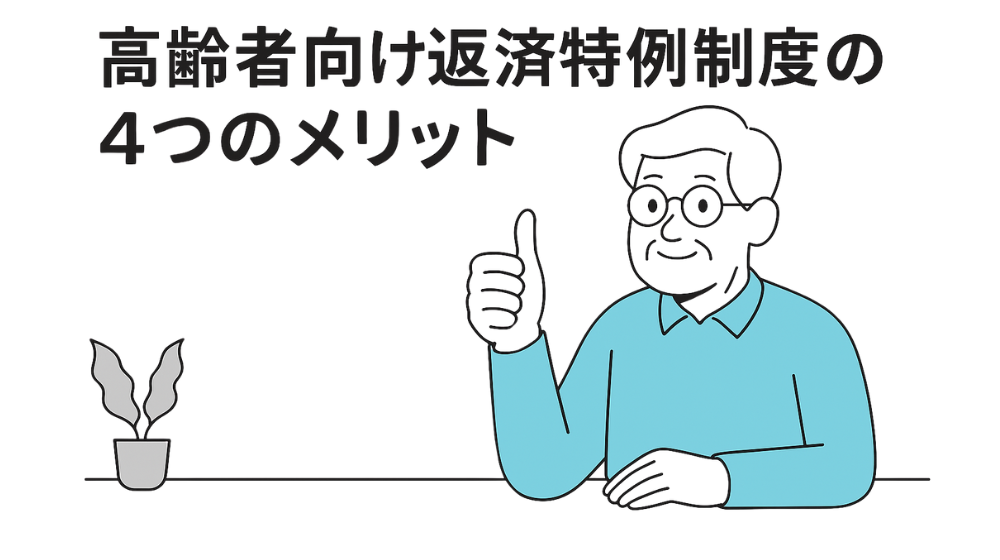
高齢者向け返済特例制度を利用することで、リフォーム資金の負担を軽減できます。
この制度には以下の4つのメリットがあります。
- 月々の返済負担が軽い
- 年齢制限が緩い
- 元金返済の柔軟性
- 保証人が不要
これらのメリットについて、詳しく解説します。
月々の返済負担が軽い
毎月の返済は利息のみで済むため、通常のローンに比べて月々の負担が大幅に軽減されます。
例えば、1,000万円借入れの場合、通常のローンでは月々約8万8,000円の返済が必要ですが、この制度では約8,700円程度で済みます。
【参考】住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)「リフォーム融資【高齢者向け返済特例】(部分的バリアフリー工事・ヒートショック対策工事・耐震改修工事)」
年齢制限が緩い
この制度では、毎月の返済が利息のみとなるため、月々の負担を大幅に軽減できます。
元金の返済は申込者全員が亡くなった際に一括でおこなわれます。
元金返済の柔軟性
この制度では、毎月の返済が利息のみとなるため、月々の負担を大幅に軽減できます。
元金の返済は申込者全員が亡くなった際に一括でおこなわれます。
保証人が不要
高齢者住宅財団が連帯保証人となるため、個人的な保証人を立てる必要がありません。
この制度は、高齢者の方々が安心して住宅改修をおこなえる仕組みです。
月々の支払いが少なく、年齢制限も厳しくなく、返済方法も選べるため、快適な老後のための住宅リフォームが実現できるでしょう。
高齢者向け返済特例制度4つのデメリット
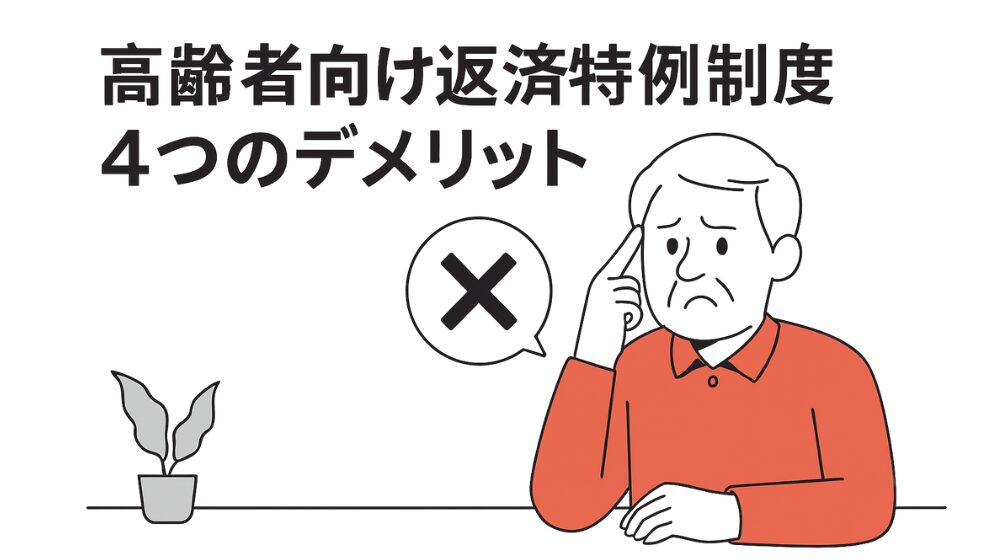
多くのメリットがある一方で、高齢者向け返済特例制度には注意すべきデメリットも存在します。
利用前に把握しておおきたい、主な4つのデメリットは下記のとおりです。
- 一括返済が必要になった時の負担が大きい
- 抵当権設定による資産活用の制限が生じる
- 相続人の同意取得に時間がかかる
- 将来の金利変動で返済負担が増加する
詳しくみていきましょう。
一括返済が必要になった時の負担が大きい
この制度では、申込者全員の死亡時に元金を一括返済する必要があります。そのため、相続人にとって大きな負担となる可能性があります。
解決策として、事前に相続人と十分な話し合いをおこない、返済計画を共有しておくことが重要です。
また、生命保険の活用や、リフォームによる住宅価値の向上を図ることで、将来的な負担を軽減できます。
抵当権設定による資産活用の制限が生じる
融資を受ける際、住宅に抵当権が設定されるため、他のローンの利用や売却が制限される場合があります。
これを解決するためには、リフォーム計画を立てる段階で、将来の資産活用の可能性を考慮し、必要最小限の融資額に抑えることが望ましいです。
また、金融機関と相談し、他の選択肢も検討することが有効です。
相続人の同意取得に時間がかかる
制度利用には、推定相続人全員の同意書が必要です。
相続人が複数いたり遠方にいたりすると、同意を得るまでに時間がかかることがあります。
相続人の理解が得られない場合、手続きが進まない可能性もあるでしょう。
解決策としては、制度利用を考え始めたら早めに相続人へ相談・説明し、理解を求めることです。
時間に余裕を持った申し込み計画を立てましょう。
将来の金利変動で返済負担が増加する
金利が変動する場合、毎月の利息返済額が増加し、家計に影響を及ぼす可能性があります。
これを防ぐためには、固定金利の選択や、金利上昇リスクを考慮した資金計画を立てることが重要です。
また、定期的に金利動向を確認し、必要に応じて専門家に相談することで、適切な対応が可能です。
このように、高齢者向け返済特例制度にはいくつかのデメリットがありますが、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑えられるでしょう。
高齢者向け返済特例制度の利用条件と申込方法

高齢者向け返済特例制度を実際に利用したいと考えたとき、まず確認すべきは「自分が利用できるのか?」という利用条件と「どうやって申し込むのか?」という手続きの方法です。
この制度には年齢や収入、対象となるリフォーム工事の種類など、いくつかの条件が定められています。
- 利用条件
- 対象となるリフォーム工事
- 申込方法と手続きの流れ
- 申込に必要な書類
それでは、利用条件からみていきましょう。
利用条件
高齢者向け返済特例制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
| 条件項目 | 要件 |
|---|---|
| 年齢条件 | 満60歳以上(上限なし) |
| 対象物件 | 自らが居住する住宅 |
| 総返済負担率 | 年収400万円未満:30%以下 年収400万円以上:35%以下 |
| 国籍要件 | 日本国籍または永住許可を持つ外国人 |
これらの条件をクリアすると、制度の利用が可能です。
対象となるリフォーム工事
この制度で対象となるリフォーム工事は、以下のいずれかを含むものです。
ご自身の計画しているリフォーム工事が対象となるか不明な場合は、事前に住宅金融支援機構や取扱金融機関、(一財)高齢者住宅財団へ問い合わせてみましょう。
申込方法と手続きの流れ
申込から融資実行までの一般的な流れ(手順)は、次のとおりです。
| 流れ(手順) | 内容 |
|---|---|
| 1. カウンセリングの受講 | 制度利用に関する説明を受ける |
| 2. 保証限度額設定の申請 | 保証機関に対し、保証限度額の設定を申請する |
| 3. 保証限度額証明書の発行 | 保証機関から証明書が発行される |
| 4. 融資・保証の申込み | 必要書類を揃え、融資と保証の申込みをおこなう |
| 5. 申込み内容の審査 | 融資機関と保証機関が審査を開始 |
| 6. 融資の決定 | 審査結果に基づき、融資の可否が決定される |
| 7. 工事の着工 | 融資決定後、リフォーム工事が開始される |
| 8. 物件調査・適合証明書の提出 | 工事完了後、適合証明書を取得し提出する |
| 9. 融資・保証の契約 | 正式な契約を締結する |
| 10. 融資金の受取、保証料などの支払い | 融資金を受け取り、必要な費用を支払う |
| 11. 返済の開始 | 毎月の利息返済がはじまる |
なお、カウンセリングから工事着工まで約2ヵ月程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで検討しましょう。
申込に必要な書類
高齢者向け返済特例制度の申し込みには、さまざまな書類が必要です。
主なものを以下に挙げますが、状況により異なる場合があるため、必ず住宅金融支援機構のWebサイトや(一財)高齢者住宅財団のカウンセリングなどで最新の情報を確認してください。
| 書類名 | 内容・詳細 |
|---|---|
| 借入申込書 | 所定の様式に必要事項を記入します |
| 収入証明書 | 最新の収入を証明する書類 |
| リフォーム工事の見積書 | 工事内容と費用が明記されたもの |
| 担保提供に関する書類 | 土地・建物の登記簿謄本など |
| 推定相続人の同意書 | 借入者死亡時の返済や担保処分に関して、法定相続人が同意した書類 |
| 保証限度額証明書 | 保証機関から発行されたもの |
書類の準備には時間がかかる場合もあるため、早めに確認・準備を進めましょう。
高齢者向け返済特例制度 | リフォーム融資の金利と返済シミュレーション

毎月の返済額は、借入希望額と適用金利に基づいて計算されます。
高齢者向け返済特例の場合、毎月の支払額(利息のみ)は下記の計算式で求められます。
借入希望額(万円) × 融資金利(年利) ÷ 12
例えば、500万円を借り入れ、年利1.27%の場合、毎月の利息支払額は次のようになります。
500万円 × 0.0127 ÷ 12 = 5,291円
このように、毎月の支払額は利息のみで、元金は借入者全員の死亡時に一括返済となります。
なお、実際の返済額は適用金利や借入額によって異なりますので、詳細なシミュレーションをおこなうことをおすすめします。
住宅金融支援機構のWebサイトでは、リフォーム融資の新規借り入れシミュレーションが提供されていますので、ぜひご活用ください。
この制度を利用することで、毎月の返済負担を抑えつつ、安心してリフォームをおこなえるでしょう。
ただし、元金の一括返済時には多額の資金が必要となるため、慎重に検討することが重要です。
【参考】住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)「【グリーンリフォームローン】・リフォーム融資 新規借り入れシミュレーション」
【参考】一般財団法人 高齢者住宅財団「リフォーム融資の債務保証」
高齢者向け返済特例制度の具体的な活用事例

高齢者向け返済特例制度は様々なシーンで活用され、多くの高齢者の住環境改善に貢献しています。
ここでは、下記にある代表的な事例を4つ紹介します。
- 70代独居高齢者の耐震改修工事の事例
- 配偶者を亡くした高齢者のバリアフリーリフォーム事例
- 世帯住宅へのリフォームを実現した事例
- 災害復興住宅融資と組み合わせた活用事例
詳しくみていきましょう。
70代独居高齢者の耐震改修工事の事例
72歳の山田さん(仮名)は、築40年の木造住宅に一人で暮らしています。
近年の地震の多発に不安を感じ、耐震改修工事を検討していましたが、年金収入だけでは通常のローンでの返済が難しい状況でした。
高齢者向け返済特例制度を利用することで、800万円の耐震改修工事を実施。
月々の返済は約8,500円の利息のみとなり、安心して工事を進めることができました。
子どもたちに負担をかけることなく、安全な住環境を手に入れることができたと喜んでいます。
配偶者を亡くした高齢者のバリアフリーリフォーム事例
75歳の佐藤さん(仮名)は、最近夫を亡くし一人暮らしをはじめました。
夫の介護で忙しく、住宅のメンテナンスが行き届いていなかったため、バリアフリー化を含む大規模なリフォームが必要な状況でした。
高齢者向け返済特例制度を利用して1,200万円の融資を受け、浴室の改修・手すりの設置・段差の解消などを実施。
月々の返済負担は約13,000円と軽く、一人暮らしに適した安全な住環境を整えることができました。
将来の不安を感じることなく、住み慣れた家で生活を続けられることに安心感を得ています。
世帯住宅へのリフォームを実現した事例
68歳の鈴木さん夫妻(仮名)は、都会に住む息子家族との同居を視野に入れて、二世帯住宅へのリフォームを検討していました。
しかし、1,500万円という高額な工事費用に躊躇していました。
高齢者向け返済特例制度を利用することで、月々の返済は約16,000円の利息のみとなり、老後資金を大きく減らすことなくリフォームを実現。
息子家族との同居が実現し、孫の成長を身近で見守れる喜びと、将来の介護の不安が軽減されました。
災害復興住宅融資と組み合わせた活用事例
80歳の田中さん(仮名)は、災害で被害を受けた住宅の修繕が必要でしたが、年齢を理由に通常の融資を断られていました。
そこで田中さんは金融機関のアドバイスを受け、災害復興住宅融資と高齢者向け返済特例制度の併用を検討。
これらの制度を組み合わせることで、必要な修繕工事と同時に耐震改修工事も実施することができました。
総額1,000万円の工事でしたが、月々の返済は約10,000円程度に抑えられ、安全で快適な住環境を取り戻すことができました。
これらの事例からわかるように、高齢者向け返済特例制度は、高齢者の多様な状況やニーズに応じたリフォーム実現の一助となっていることがわかります。
次に、高齢者向け返済特例制度に関する「よくある質問」をみていきましょう。
高齢者向け返済特例制度に関するよくある質問
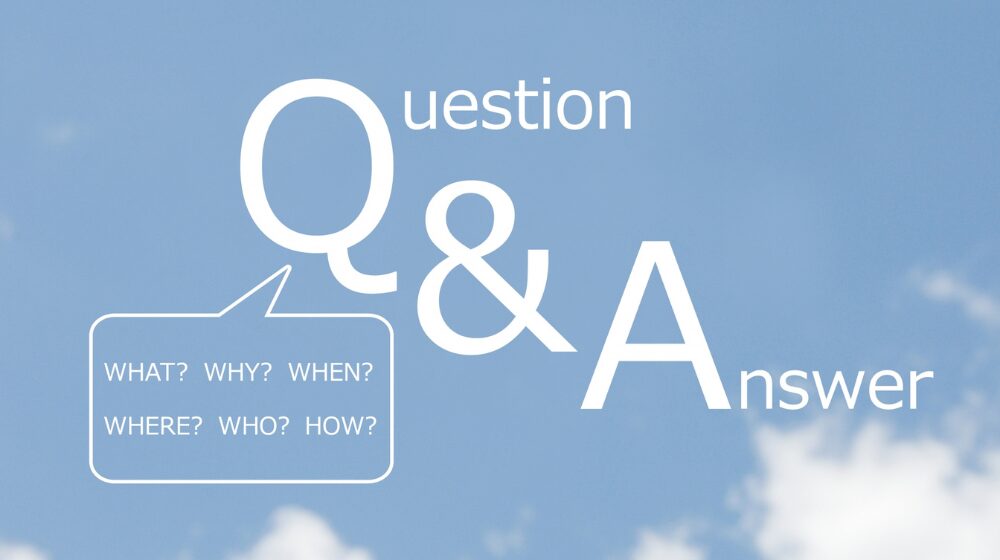
高齢者向け返済特例制度に関して、よくある質問と回答をまとめました。
制度についての疑問点を解消し、制度利用の判断材料としていただければ幸いです。
Q1. 返済特例制度では融資限度額(上限)はいくらまでですか?
A1. 本制度の融資限度額は次のとおりです。
- 一戸建て住宅の場合:土地および建物の価格の60%または1,500万円のいずれか低い額
- マンション等の場合:構造により異なり、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は土地および建物の価格の50%、その他の構造の場合は25%、または1,500万円のいずれか低い額膠腫剤協会
【参考】一般財団法人 高齢者住宅財団「高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資) よくあるご質問」
ただし、保証機関が定める保証限度額や実際のリフォーム工事費用も考慮され、最終的な融資額はこれらのうち最も低い金額となります。
Q2. 返済特例制度はどの地域でも利用可能ですか?
A2. 本制度は日本全国で利用可能です。ただし、担保物件の評価や地域の特性により、保証限度額が変動する場合があります。
【参考】一般財団法人 高齢者住宅財団「高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資)よくあるご質問」
Q3. 他の融資制度と比較して、高齢者向け返済特例制度の優位性は何ですか?
A3. 高齢者向け返済特例制度の主な優位性は下記のとおりです。
- 月々の返済負担が軽減:生存中は利息のみの返済で、元金は死亡時に一括返済される
- 年齢制限の緩和:満60歳以上であれば利用可能で、上限年齢は設定されていない
- 保証人不要:住宅金融支援機構が承認する保証機関の保証を受けることで、保証人なしで融資を受けることが可能
高齢者向け返済特例制度の利用を検討される際は、個人の状況により条件や手続きが異なるため、住宅金融支援機構や(一財)高齢者住宅財団の窓口、または本制度に詳しい専門家に必ず相談しましょう。
【まとめ】高齢者向け返済特例制度で安心なリフォーム計画を実現しよう

住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例制度」は、満60歳以上の方が利息のみの毎月返済で自宅をリフォームできる公的な融資制度です。
年齢上限がなく月々の負担も軽いため、高齢者でも利用しやすい点が大きなメリットといえます。
ただし、将来の元金一括返済は相続人に影響し、自宅への抵当権設定や金利変動リスクも考慮する必要があります。
制度を正しく理解し賢く活用して安心なリフォーム計画を実現するために、まずは本制度に詳しい専門家へ問い合わせてみましょう。
【高齢者向け返済特例制度を利用してリフォームを検討されている方々へ】
株式会社昇永がサポートいたします。
弊社はシニアライフサポートの専門家として、生前整理・遺品整理、高齢者向け施設の紹介、不動産売買や解体工事・リフォームなど、高齢者の生活を総合的に支援しております。
当社の強みは下記のとおりです。
【ワンストップサービス】
お片付けから施設紹介、不動産売買まで、高齢者に関するあらゆる問題を一貫して解決できる体制を整えております。
【専門性の高さ】
シニアライフ専門の相談員が在籍し、法律家や医療専門家とも連携することで、質の高いサービスを提供しています。
【柔軟な顧客対応】
画像・動画による見積もりやオンライン相談にも対応し、顧客のニーズに合わせた柔軟な対応を心がけています。
高齢者向け返済特例制度の利用を検討されている方は、ぜひご相談ください。
