「まさか親が…」急な入院の連絡に、頭が真っ白になった経験はありませんか?
高齢の親を持つ私たちにとって、親の入院は決して他人事ではありません。
この記事では、親が急に入院することになった場合に、慌てずに対応するための準備・費用・手続き・お金に関する情報をまとめて解説します。
この記事を読めば、いざという時に冷静に対応できるようになり、親の入院に対する不安を少しでも軽減できるでしょう。
- 高齢の親を持つ方
- 親の入院に不安を感じている方
- 親の入院に備えたいと考えている方
- 親がもうすぐ入院する方
- 入院に関する手続きや費用について知りたい方
- 親の入院に必要な準備がわかる
- 入院費用に関する不安が解消される
- 入院手続きの流れが理解できる
- 入院費用を工面する方法がわかる
- 万が一の際に役立つお金の準備ができる
- 親の入院に際して、落ち着いて行動できるようになる
親の入院に備えるための【事前準備】

親の入院は、いつ起こるかわからないものです。
いざという時に慌てないためにも、日頃から備えておくことが大切です。
ここでは、入院前に準備しておくと安心な5つのポイントを詳しく解説します。
1.入院時に必要なものをリストアップ
入院時に必要なものは、病院によって多少異なりますが、共通して必要となるものがあります。
事前にリストアップしておくことで、急な入院時にもスムーズに対応できます。
下記のリストを参考に、ご家庭で必要なものを確認し、いつでも持ち出せるように準備しておきましょう。
- 保険証、診察券
- 入院手続きに必須です。コピーではなく、必ず原本を用意しましょう。
- 印鑑
- 各種書類へのサインや捺印に使用します。シャチハタではなく、認印を用意しましょう。
- 着替え、下着、パジャマ
- 数日分の着替えを用意しましょう。前開きのパジャマは、医療処置の際にも便利です。
- 洗面用具、タオル
- 歯ブラシ・歯磨き粉・コップ・石鹸・シャンプー・タオルなどを用意しましょう。
- ティッシュ、ウェットティッシュ
- 何かと使う場面が多いので、多めに用意しておきましょう。
- お箸、スプーン
- 病院で用意されている場合もありますが、使い慣れたものがあると便利です。
- イヤホン
- 同室の方に配慮し、テレビや音楽を聴く際に使用します。
- 充電器
- スマートフォンやタブレットなど、充電が必要な場合は、必ず用意しましょう。
- お薬手帳
- 服用中の薬を医師に伝えるために必要です。 薬の名前だけでなく、服用量や服用時間も正確に記入しておきましょう。
- その他(病院から指示されたもの)
- 病院によって、別途用意が必要なものがある場合があります。 入院前に、病院からの指示をよく確認しましょう。
これらのリストを参考に、必要なものをリストアップし、すぐに用意できるように、入院セットをまとめておくと便利です。
また、病院によってはレンタルできるものもあるので、事前に確認しておくと、荷物を減らすことができます。
2.緊急連絡先リストを作成
親が入院した場合、ご家族や親戚、親しい友人など、さまざまな人に連絡が必要となる可能性があります。
事前に連絡先リストを作成しておくことで、スムーズな情報共有が可能です。
リストには、以下の情報を記載するようにしましょう。
- 名前
- 続柄
- 電話番号(自宅、携帯)
- メールアドレス
連絡先リストは、紙に書いておく以外にも、スマートフォンの連絡先アプリに登録しておくこともおすすめです。
また、親の同意を得て、連絡先リストを家族間で共有しておくことで、緊急時にも迅速な対応が可能です。
3.健康保険証、医療証、お薬手帳を保管場所を把握
入院手続きには、親の健康保険証、医療証(お持ちの場合)、お薬手帳が必ず必要になります。
これらの書類の保管場所を把握しておかないと、緊急時に入院手続きがスムーズにおこなえなくなってしまう可能性があります。
普段から、これらの書類は一箇所にまとめて保管し、保管場所を家族で共有しておくと、いざという時に安心です。
また、コピーをとっておき、すぐに取り出せる場所に保管しておくのもおすすめです。
4.親の既往歴、アレルギー情報を把握
親の既往歴(過去の病歴)やアレルギー情報は、入院時に医師に正確に伝える必要があります。
これらの情報が正確でないと、適切な治療が受けられなくなる可能性があります。
これらの情報を、普段からメモや手帳に控えておきましょう。
また、かかりつけ医の名前、連絡先、診療科も記録しておくと、よりスムーズな連携が可能です。
これらの情報は、紙に記録する以外に、スマートフォンのメモアプリに記録しておくと、必要なときにすぐに見ることができます。
5.入院費用の目安を知っておく
入院費用は、病気の種類、入院期間、治療内容、個室の利用などによって大きく異なります。
事前に大まかな目安を把握しておくことで、入院費用の準備をスムーズに進めることができます。
生命保険文化センターの2022年度の調査によると「入院費(自己負担額)」は、19.8万円で、およそ7割が20万円未満という結果でした。
1回の入院費用に準備する費用は、おおよそで20万円の自己負担だと心得ておくと良いでしょう。
実際の入院費用は、病院や個人の状況によって大きく異なりますので、事前に病院に確認しましょう。
【参考】公益財団法人生命保険文化センター|入院費用(自己負担額)はどれくらい?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報
入院費用の【基礎知識】と【節約術】

入院費用は、病気や怪我の種類、治療内容、入院期間などによって大きく変動するため、費用が心配になる方も多いでしょう。
しかし、公的な制度や賢い節約術を知っていれば、入院費用の負担を大きく軽減することができます。
ここでは、入院費用を抑えるための基礎知識と具体的な節約術について解説します。
1.医療費の自己負担割合を確認
医療費の自己負担割合は、年齢や所得によって異なります。
まずは、親の自己負担割合が何割になるのかを事前に確認しておきましょう。
自己負担割合を把握することで、入院費用の目安を立てやすくなり、支払いの準備もスムーズにおこなえます。
【自己負担割合の例】
| 年齢区分 | 自己負担割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 70歳未満 | 3割 | 原則として、医療費の3割を自己負担します。 |
| 70歳以上75歳未満 | 2割 (一定以上の所得者は3割) | 原則として、医療費の2割を自己負担します。ただし、一定以上の所得がある場合は3割負担となります。 ※一定以上の所得とは、課税所得が145万円以上の方や、住民税課税世帯で年収383万円以上の方などが該当します。 |
| 75歳以上 | 1割 (一定以上の所得者は3割) | 原則として、医療費の1割を自己負担します。ただし、一定以上の所得がある場合は3割負担となります。 ※一定以上の所得とは、課税所得が145万円以上の方や、住民税課税世帯で年収383万円以上の方などが該当します。 |
自己負担割合は、保険証に記載されているので、確認しておきましょう。
また、市区町村によっては、独自の医療費助成制度がある場合もありますので、お住まいの自治体にも確認してみましょう。
2.高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた部分が払い戻される制度です。
この制度を活用することで、入院費用の自己負担を大幅に軽減できます。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
ご自身の限度額を事前に確認しておきましょう。
例えば、
- 70歳未満の方: 年収が高ければ高いほど、自己負担限度額も高くなります。
- 70歳以上の方: 70歳未満の方よりも、自己負担限度額は低く設定されています。また、年収だけでなく、所得区分によっても細かく設定されています。
【自己負担限度額早見表】
| 年齢 | 所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担限度額 (月額) |
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 年収約370万円未満 | 3割 | 57,600円 |
| 70歳未満 | 年収約370万円~770万円 | 3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 70歳未満 | 年収約770万円~1,160万円 | 3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 70歳未満 | 年収約1,160万円以上 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 70~74歳 | 課税所得145万円以上(年収約370万円~) | 3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 70~74歳 | 課税所得145万円未満(年収約370万円未満) | 1割 | 44,400円 |
| 75歳以上 | 現役並み所得者(年収約370万円~) | 3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 75歳以上 | 現役並み所得者以外(年収約370万円未満) | 1割 | 44,400円 |
【参考】厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
高額療養費制度は、自動的に適用されるものではなく、申請が必要な場合があります。
詳しくは、加入している健康保険組合や市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
3.限度額適用認定証の活用
限度額適用認定証とは、医療機関の窓口で支払う医療費を、自己負担限度額までにとどめることができる証明書です。
事前に加入している健康保険組合や市区町村の窓口で申請することで交付されます。
高額療養費制度は、医療費を支払った後で払い戻しを受ける制度ですが、限度額適用認定証を利用すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
特に、入院や手術など、医療費が高額になることが事前にわかっている場合は、必ず限度額適用認定証を申請しましょう。
70歳以上の方の場合、申請が必要ないケースもありますが、ご自身の状況を確認しておきましょう。
4.医療費控除の活用
医療費控除とは、1年間の医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除を受けることで、所得税や住民税を減額することができ、結果的に医療費の負担を軽減することができます。
医療費控除の対象となる医療費は、自分自身だけでなく、生計を同一にする配偶者や親族の医療費も含まれます。
また、医療費控除は、確定申告をおこなうことで適用されます。
医療費の領収書は、必ず保管しておきましょう。
【参考】国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
5.ジェネリック医薬品の活用
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許期間が満了した後に、同じ有効成分で製造される後発医薬品のことです。
先発医薬品に比べて価格が安く、医療費を抑える効果が期待できます。
医師や薬剤師に相談し、ジェネリック医薬品への切り替えを検討してみましょう。
ただし、ジェネリック医薬品は、先発医薬品と全く同じものではないため、医師や薬剤師に相談し、ご自身の症状に合った薬を選ぶようにしましょう。
6.その他医療費を抑える方法
上記以外にも、日頃から医療費を抑えるための工夫を心がけましょう。
- 調剤薬局を比較する
- 調剤薬局によって、調剤基本料や薬の価格が異なる場合があります。複数の薬局を比較検討することで、薬代を節約できる場合があります。
- 入院費用が高い場合は、相談窓口で減免制度について相談する
- 医療費の支払いが困難な場合は、病院の相談窓口や自治体の相談窓口に相談してみましょう。 医療費減免制度や医療費貸付制度を利用できる場合があります。
入院【手続き】の流れと注意点
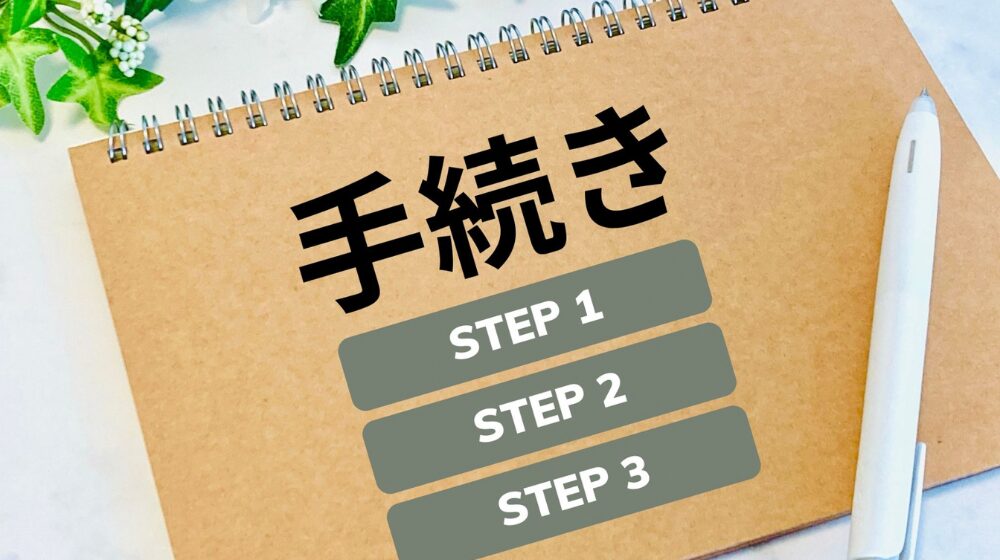
入院が決まったら、速やかに手続きを進める必要があります。
しかし、初めての入院の場合、どのような手続きが必要なのか、何に注意すればよいのか不安に感じる方もいるでしょう。
ここでは、入院手続きの流れと注意点について詳しく解説します。
1. 病院からの指示に従う
入院が決まると、病院の担当者から入院手続きに関する説明があります。
入院手続きに必要な書類や持ち物、入院スケジュール、入院生活における注意事項など、説明内容は多岐に渡ります。
説明を聞く際には、メモを取りながら、不明な点や疑問点は遠慮せずに質問するようにしましょう。
特に、入院当日の集合時間や場所、病室・食事・貴重品の管理・面会時間など、入院生活に直結する情報はしっかりと確認しておきましょう。
また、病院によっては、入院説明会を実施している場合もあるので、積極的に参加することをおすすめします。
2. 入院手続きに必要な書類
入院手続きには、以下の書類が必要になります。
- 入院申込書
- 病院で渡される入院申込書に、氏名、生年月日、住所などの必要事項を記入します。
- 健康保険証
- 国民健康保険、健康保険組合などの被保険者証が必要です。原本を必ず持参しましょう。
- 医療証(お持ちの方)
- 乳幼児医療費助成、障害者医療費助成など、医療費の助成を受けている方は、医療証も持参しましょう。
- 限度額適用認定証(お持ちの方)
- 高額療養費制度を利用する方は、限度額適用認定証を提出することで、窓口での医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
- 印鑑
- 入院誓約書などの書類に捺印するために必要です。シャチハタではなく、認印を用意しましょう。
- その他(病院から指示されたもの)
- 病院によっては、上記以外にも、入院時に必要な書類や持ち物を指定する場合があります。 事前に病院からの指示を確認し、忘れ物がないように準備しましょう。
事前に準備しておくと、スムーズに入院手続きを完了することができます。
3. 入院時の保証人について
入院時には、連帯保証人を求められる場合があります。
保証人は、入院費用の支払い債務や、入院中の親の責任を保証する役割を担います。
保証人になれるのは、親族の場合が多いですが、病院によって規定が異なるため、事前に確認しておきましょう。
もし、親族に保証人を頼めない場合は、病院の相談窓口に相談しましょう。
保証会社を利用できる場合や、他の方法を提案してもらえる場合があります。
4. 入院費用の支払い方法
入院費用の支払い方法は、病院によって異なります。
入院手続きの際に、支払い方法について確認しておきましょう。 主な支払い方法としては、以下のものが挙げられます。
- 現金払い
- 病院の窓口で現金を支払う方法です。
- クレジットカード払い
- クレジットカードで支払う方法です。利用できるカードの種類は病院によって異なります。
- 銀行振込
- 病院が指定する口座に、銀行振込で支払う方法です。
また、高額な医療費となる場合は、医療費の分割払い制度や、医療費貸付制度を利用できる場合があります。
支払い方法についても、病院の窓口に相談してみましょう。
親の入院に備える【お金】の準備
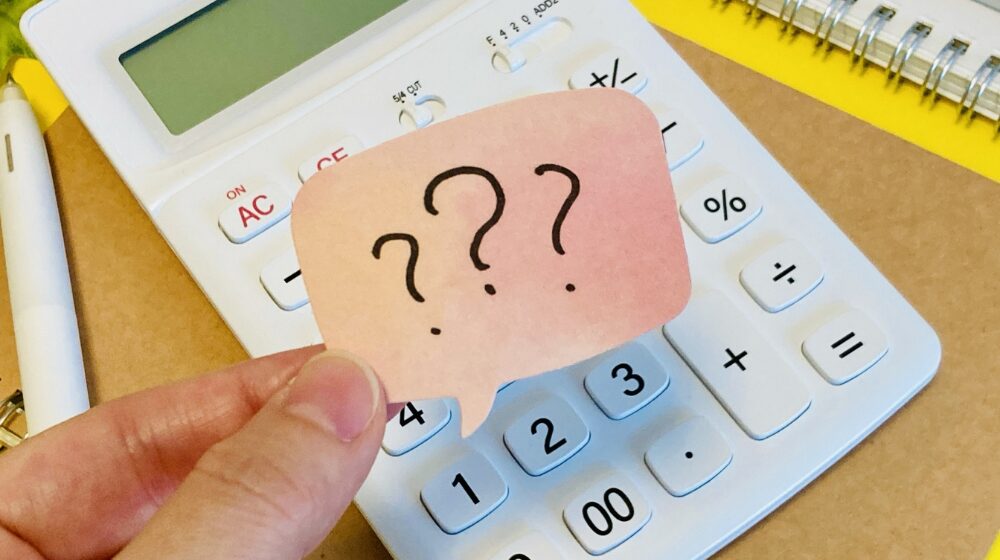
親の入院は、予期せぬ出費をともなうことがあります。
入院費用をスムーズに工面するためには、事前に準備しておくことが大切です。
ここでは、入院費用の目安や工面する方法、そして、万が一の時に役立つお金の準備について詳しく解説します。
1. 入院費用の目安
入院費用は、病気の種類、治療内容・入院期間・個室の利用などによって大きく変動するため、一概にいくらとはいえません。
しかし、事前に大まかな目安を知っておくことは、費用の準備をスムーズに進める上で重要です。
下記に、一般的な入院費用の例をまとめました。
ただし、これはあくまで目安であり、個人の状況によって変動することを理解しておきましょう。
【入院費用例】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 個室料(差額ベッド代) | 1日あたり5,000円〜30,000円程度 |
| 食事代 | 1食あたり500円程度 |
| 治療費 | 病状により変動 |
| 雑費 | 日用品、テレビカードなど |
入院費用は、これらの項目以外にも、交通費・付き添い人の費用、退院後のリハビリ費用なども考慮する必要があります。
入院前に、できる限り詳細な費用の見込みを立てておくことが大切です。
2. 入院費用を工面する方法
入院費用を工面する方法は、いくつかあります。
事前に、どの方法で費用を工面するか検討しておきましょう。
- 預貯金
- 日頃から、入院費用を想定して、預貯金をしておくのが理想的です。 万が一の場合に備えて、ある程度の金額を確保しておきましょう。
- 生命保険
- 加入している生命保険に、入院保障や手術給付金が含まれているか確認しましょう。 保険契約の内容によっては、入院費用の負担を軽減できる場合があります。
- 医療保険
- 医療保険に加入している場合は、入院給付金や手術給付金が支給される場合があります。 保険契約の内容を確認し、必要な保障があるか確認しましょう。
- 高額療養費制度
- 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた部分が払い戻される制度です。 この制度を活用することで、入院費用の自己負担を軽減することができます。
- 医療費貸付制度
- 医療費の支払いが困難な場合に、無利子または低金利で医療費を借りることができる制度です。 自治体や社会福祉協議会などで利用できる場合があります。
これらの方法を組み合わせることで、入院費用の負担を軽減できます。
どの方法が自分に合っているか、事前に検討しておきましょう。
3. 代理人カードの準備
入院中の親が、ご自身で銀行にお金を引き出しに行くことが難しい場合があります。
代理人カードを事前に準備しておくと、親の代わりに、ご家族がお金を引き出すことができます。
代理人カードの作成には、親の本人確認書類や印鑑などが必要になります。
手続きに時間がかかる場合もあるので、事前に準備しておくことをお勧めします。
また、代理人カードの使用限度額や、利用規約についても、事前に確認しておきましょう。
4. 生命保険や医療保険の見直し
加入している生命保険や医療保険は、定期的な見直しが大切です。
保険契約の内容が、現在のライフスタイルや家族構成、健康状態に適しているか確認してください。
特に、親の年齢が上がるにつれて入院や手術のリスクが高まるため、入院保障や手術給付金が充実した保険への加入がおすすめです。
また、保険料が負担になっている場合は、保障内容を見直して保険料を抑えることも必用です。
保険の見直しをする際は、保険会社や保険代理店に相談してみましょう。
ご自身の状況に合った保険を選択することが重要です。
【まとめ】急な入院に慌てないために「できることを今すぐ始めよう」
この記事では、親が急に入院することになった場合に、慌てず、冷静に対応するための準備・費用・手続き・お金に関する情報をまとめて解説しました。
入院は、誰にでも起こりうることであり、決して他人事ではありません。
この記事を参考に、まずはできることから少しずつ準備を始めましょう。
今日から、この記事でお伝えした以下の5つのポイントを参考に、行動に移してみましょう。
- 入院時に必要なものをリストアップして準備する
- 緊急連絡先リストを作成して家族で共有する
- 健康保険証・医療証・お薬手帳の保管場所を把握する
- 親の既往歴やアレルギー情報を把握する
- 入院費用の目安を把握する
事前の準備をしっかりとしておくことで、いざという時に冷静に対応でき、親の不安を少しでも軽減できるだけでなく、ご自身の負担も減らすことができます。
また、この記事で紹介した制度や情報を活用することで、経済的な負担も軽減できるはずです。
この記事が、あなたとあなたの大切なご家族のお役に立てれば幸いです。
そして、一日でも早く、ご家族の笑顔が戻ることを心より願っています。
株式会社昇永の紹介

この記事では、親御さんの急な入院に備えるためのさまざまな情報をお伝えしましたが、入院後の生活や、万が一の時の相続・財産管理についても、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
株式会社昇永では、相続・終活サポート、不動産コンサルティング、成年後見・遺言書作成サポートなど、お客様の状況に合わせたきめ細やかなサポートをご提供しています。
もし、少しでも不安を感じているようでしたら、まずは無料相談をご利用ください。
電話、メール、LINEでのお問い合わせを24時間受け付けています。
\ 安心の老後は、昇永から始まります! /
あなたの「備えあれば憂いなし」をサポートします。
株式会社昇永で、次の一歩を踏み出しましょう。

関連記事
高齢者の身元保証トラブル解決法 – 専門家が教える対策と注意点
